【みんなの名字の由来】
「みんなの名字の由来」は各名字の検索結果ページから登録できます。
名字検索はこちらからどうぞ。
「みんなの名字の由来」は各名字の検索結果ページから登録できます。
名字検索はこちらからどうぞ。

スポンサーリンク
| 鳥居南さん |
|---|
解説のとおり、京都府出身の宮司さんです。

|
| 【投稿日】2024/06/13 08:32:27 【投稿者】ちば子さん |
| 河越さん |
|
桓武平氏秩父氏流河越氏は、川越・河肥とも表記される。 平安時代末期から南北朝時代にかけて武蔵国で勢力を張った豪族の氏族である。 坂東八平氏秩父氏の嫡流に相当し、河越館(現埼玉県川越市上戸)を拠点として、国司代理職である「武蔵国留守所総検校職」を継承、武蔵国在庁筆頭格として、武蔵七党等中小武士団や国人を取りまとめていたとされる。 後三年の役で先陣を勤めた功績により発展した秩父氏嫡流である河越氏は、秩父重綱以降、代々「武蔵国留守所総検校職」を勤める有力在庁官人であり、武蔵国の武士団の顔役となった。 河越氏の祖・秩父重隆は、秩父氏家督である総検校職を継承するが、兄・重弘の子で甥の畠山重能と家督を巡って対立、おりから近隣新田氏、藤姓足利氏と抗争を繰り返しており、東国に下向した河内源氏源義賢に娘を嫁がせ、大蔵の館に「養君」として迎えることで周囲の勢力と対抗を画策した。久寿2年(1155年)8月16日、大蔵合戦により、源義朝・義平親子と結んだ畠山重能らによって重隆・義賢が討たれると、秩父平氏本拠であった大蔵は、ライバル畠山氏に奪われる事となり、重隆の嫡男・能隆と孫の重頼は新天地の葛貫(現埼玉県入間郡毛呂山町葛貫)や河越(川越市上戸)に移転、河越館を拠点として河越氏を名乗るようになった。本拠大蔵は奪われたものの、総検校職は重頼に継承。 保元元年7月(1156年)保元の乱において、重頼と弟の師岡重経が源義朝の陣営に加わっており、河越・師岡は『保元物語』で「高家」と称されている。平治元年(1159年)12月の平治の乱で源義朝が滅びたのち平家に恭順。永暦元年(1160年)頃平家を介して所領を後白河上皇に寄進、新日吉社(新日吉神宮)領として河越荘が立荘、本家を新日吉社、本所を後白河院として河越氏はその荘官となる。平治の乱後に義朝の子源頼朝が東国へ配流と裁定され、その乳母比企尼が頼朝を援助するために武蔵国へ下向、重頼は比企尼次女(河越尼)を妻に迎えたことにより、頼朝の援助を行う役目を負い、伊勢平氏に従いながら引き続き河内源氏とも繋がりを有した。 頼朝による反平家反乱である治承4年(1180年)の治承寿永の乱では、当初平家方として参戦するも、のちに同族畠山氏・江戸氏らと同様頼朝に臣従。頼朝政権下での重頼は妻が頼朝の嫡子・頼家誕生の際に乳母として召されており、娘(郷御前)が頼朝の弟・源義経の正室となったため、比企氏との繋がりによって重用された。嫡男重房は義経側近として『平家物語』にも活躍が描かれる。しかし頼朝と義経が対立すると、義経縁戚であることを理由に、重頼・重房父子は誅殺されてしまい、最終的に武蔵国留守所総検校職の地位も重能の子・畠山重忠に奪取される。 鎌倉時代の河越氏は逼迫にさらされたものの、元久2年(1205年)6月の畠山重忠の乱において重頼遺児重時・重員兄弟が北条義時率いる重忠討伐軍に加わり、御家人として中興することとなる。家督を継いだ重時は将軍随兵として幕府行事に参列、弟重員は承久3年(1221年)の承久の乱で幕府軍として戦い、武功をあげた。畠山重忠が滅んで20年後嘉禄2年(1226年)4月、幕府により重員が留守所総検校職に任じられ、総検校職は再び40年ぶりに河越氏に戻った。しかし重員が武蔵国衙に関与した形跡は既になく、武蔵守兼ねる執権北条氏の実質的支配が機能していた南関東において、総検校職は名誉のみに形骸化しており、既に実権を伴っていなかったとみられる。 『吾妻鏡』承久3年5月21日条承久の乱において、武蔵国武士団動員に際し、武蔵国衆は幕府に対して「変心」する可能性がある事が示唆され、幕府はかつて軍事指揮権が付随していた総検校職を、伝統的な地元在庁有力者であった河越氏に再任することで協調をはかり、武蔵武士団再編成と統率に臨もうとしたと考えられている。同時に本来秩父氏および河越氏の家督であった総検校職を、当主の重時ではなく、弟の重員に与える事により、巧妙に勢力を削ぐことも考慮されている。総検校職は重員の子重資に継承されるものの、その後官職の存在は不明瞭化する。 異説として河越氏の分裂は、河越重頼と本来の嫡男である重房が突如誅殺された影響で重時(次郎)の系統と重員(三郎)の系統が嫡流を巡って争った結果とする見方もある。この説によれば上戸河越館とは別に、後世川越台地と呼ばれる地域に分裂した河越氏の本拠があり、それが後世の河越城の源流となった可能性があるとされる。 重時の系統は河越氏嫡流として北条氏得宗家から受偏諱、子の泰重、孫の経重は常に将軍随兵として鎌倉で活動しており、河越館からは鎌倉と同じ文化水準の生活をうかがわせる出土品が見られるなど御家人層没落が顕著となる鎌倉後期にも、富裕な有力御家人としての地位を維持している。 元寇の頃には宗重が地頭として豊後国へ下向。鎌倉末期の元弘元年(1331年)元弘の乱では宗重の弟の貞重が、幕府軍代表として在京御家人20人に選定、六波羅探題滅亡時に幕府軍として自害した。その子・高重は結局倒幕側に転じ、武蔵七党と共に新田義貞の挙兵に加り、倒幕に貢献。 しかしながら南北朝時代の正平7年/文和元年(1352年)、観応の擾乱直後の武蔵野合戦において、高重の子・直重らは足利尊氏方に参戦、新田義宗を越後に敗走させる。その後、関東管領畠山国清の下で戦功を挙げ、相模国守護職となった。ところが関東の足利体制を固める鎌倉公方・足利基氏の下で康安2年(1362年)に畠山国清が突如失脚。その影響で河越氏の相模国守護職も解任に至る。 一変して貞治6年(1367年)4月、足利基氏は遺言で嫡子金王丸(足利氏満)の将来を、かつて冷遇した河越治部少輔らに託したことが契機となり、ついに翌貞治7年(1368年)2月、河越氏が中核となって高坂氏と共に武蔵平一揆を指揮。関東管領・上杉憲顕に大規模な地域反乱を起こした。河越館に立て籠もり数か月にわたって抵抗を続けるが、河越合戦で上杉朝房軍との激戦ののち、結局は敗北、南朝方北畠氏を頼って伊勢国へと敗走した。かくして平安時代以来武蔵国最大の勢力を誇った名族・河越氏は没落に至った。 河越氏は平安末期以降、中央からの知行国主や幕府などに、伝統ある国衙在庁出身の有力武士と認識され続け、そのために源氏、北条氏、足利氏ら、軍事貴族から派生した時の軍事権力者に翻弄され続ける結果となった。 応永20年(1413年)熊野那智大社の記録に「武蔵河越一門」という記録が見られるなど、族滅は逃れているようである。 同族に葛貫氏、庶流に小林氏、師岡氏、河野氏などがある。 |
| 【投稿日】2024/06/13 07:22:16 【投稿者】匿名さん |
| 東長田さん |
|
沖縄県石垣市大浜に、この名字の者が多い。
石垣島の東側、海に近い地域に多く住んでいる。 沖縄の本土復帰に伴い、3文字性の「東長田」から、本土でもある「東田」に改姓した親戚もいる。 |
| 【投稿日】2024/06/12 23:37:41 【投稿者】ともともさん |
| 𠮷嗣さん |
| 福岡にいます |
| 【投稿日】2024/06/12 22:20:20 【投稿者】中古賀さん |
| 早水口さん |
|
早水口さんに聞いてきました。
八代市坂本町の鮎帰地域に、早水(そうみ)という集落があります。 早水口さんの先祖はそこ出身とのことです。 |
| 【投稿日】2024/06/12 21:11:22 【投稿者】やんまーさん |
| 倭姬󠄁宮さん |
|
初めまして!
本人が直接送るなんてあまりないかと思いますが、私の苗字が御社のサイトに掲載されていないので、掲載していただきたくご連絡差し上げました。 私は、東京都は千代田区の出身でございます。 |
| 【投稿日】2024/06/12 19:53:59 【投稿者】Ju361さん |
| 泉谷さん |
|
青森県五所川原市金木町川倉の泉谷のルーツです。 金木町南台寺の泉谷家の古い墓石には「和泉屋」と刻まれてます。 元は浪岡北畠氏の家臣の「和泉氏」でしたが 大浦(津軽)氏が浪岡城を攻略して、北畠氏は滅亡し 文禄 3年(1594)に川倉に白川氏、中谷氏と一緒に開拓民として入植した、という伝えがあります 関ヶ原の前、豊臣秀吉の朝鮮出兵の頃です |
| 【投稿日】2024/06/12 19:18:38 【投稿者】いずさん |
| 紙刷さん |
| 読み方:かみすき |
| 【投稿日】2024/06/12 17:53:46 【投稿者】即さん |
| 追賜さん |
| 読み方は分からないが置賜(おいたま)の異形の可能性あり |
| 【投稿日】2024/06/12 17:50:14 【投稿者】即さん |
| 簗さん |
|
下総国結城郡(栃木県小山市)簗村発祥。元々、結城郡の郡司と推定されている。(結城市史)結城氏の譜代の家臣として結城合戦、結城氏新法度に名前がみられる。徳川家康の次男が結城秀康として養子に入り、その後、福井県、島根県など福井松平系の大名の家臣にもみられる。
簗氏には結城系と宇都宮氏庶流の二系統があるが、秋田および大分にはこの二系統の子孫が残る。 |
| 【投稿日】2024/06/12 16:45:08 【投稿者】JUNさん |
| 順位 | 日別TOP10 | 月間TOP10 |
|---|---|---|
| 1 | 貴宝院 | 佐藤 |
| 2 | 唐牛 | 鈴木 |
| 3 | 佐藤 | 田中 |
| 4 | 宇呂 | 七五三掛 |
| 5 | 黒嵜 | 高橋 |
| 6 | 槇 | 神 |
| 7 | 鈴木 | 山田 |
| 8 | 田中 | 伊藤 |
| 9 | 宝島 | 山本 |
| 10 | 山田 | 小鳥遊 |
| 1 | 夫婦は別姓だった |
| 2 | 日本のkamonはすばらしい文化遺産 |
| 3 | 名前は一つだけ |
| 1 |

|
松平 |
| 2 |

|
赤尾 |
| 3 |

|
豊泉 |
| 4 |

|
小畑 |
| 5 |

|
古宮 |

| ■新着・更新 | ■情報求む |
|---|---|
| 能勢山 | 紙刷 |
| 豊島 | 追賜 |
| 板谷 | 掛碆 |
| 立錦 | 柰園 |
| 長岩 | 𨑕田 |
| 手島 | 䓔原 |
| 宮住 | 古賀茶屋 |
| 春日 | 山西 |
| 井上 | 𠮷嗣 |
| 目串 | 棡 |
| ■名字関連ニュース |
|---|
| ■世界の富裕層が日本の不動産を… |
| ■「虎に翼」留学生役のハ・ヨン… |
| ■名札広がる「名字のみ」 背景… |
| ■【清水】17歳西原源樹に「西… |
| ■どこからがカスハラ? 客によ… |
| ■「木刀持ってぶち破っても」伊… |
| ■【山形】自治体職員の「名札」… |
| ■「家はわかる。嫁いるだろ」職… |
| ■ABC新人PR部員が何よりも… |
| ■位牌の苗字が血の色でにじむ…… |
| 名前 | ジャンル | 共有 |
|---|---|---|
| 杉原 輝雄 | スポーツ選手 |
ツイート
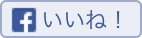
|
| 下河辺 俊行 | 経営者 |
ツイート
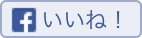
|
| 安倍 洋子 | その他 |
ツイート
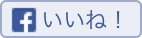
|
| 土江 寛裕 | スポーツ選手 |
ツイート
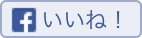
|
| 吉田 真紀 | 芸能人 |
ツイート
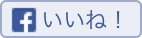
|
※ランダムで5名表示されます。今日誕生日の有名人一覧へ
| 順位 | 名前 | 生年月日 | ジャンル |
|---|---|---|---|
| 1 | 唐牛 健太郎 | 1937年 2月 11日 | その他 |
| 2 | 黒嵜 想 | 1988年 | 文学者 |
| 3 | 丹藤 昌治 | 医学 | |
| 4 | 横浜 流星 | 1996年 9月 16日 |
芸能人
|
| 5 | 植松 咲衣 | 1999年 3月 31日 |
芸能人
|
| 6 | 朽木 元綱 | 1549年 | 歴史 |
| 7 | 諸井 克英 | 1952年 | 研究者 |
| 8 | 寺戸 伸近 | 1980年 9月 9日 | スポーツ選手 |
| 9 | 唐牛 敏世 | 1879年 8月 15日 | 経営者 |
| 10 | 西宮 秀紀 | 1952年 | 研究者 |
| 順位 | 名前 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 中崎 諒 | およそ3人 |
| 2 | 佐藤 文允 | およそ3人 |
| 3 | 小澤 夫美雄 | およそ3人 |
| 4 | 前田 信吾 | およそ3人 |
| 5 | 藤井 きさ | およそ3人 |
| 6 | 鎌田 優 | およそ60人 |
| 7 | 成沢 光子 | およそ3人 |
| 8 | 平野 睦 | およそ3人 |
| 9 | 森 勇夫 | およそ3人 |
| 10 | 甲斐 光男 | およそ3人 |
※午前0時起算です。続きはこちら
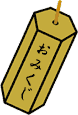
| 年 | できごと |
|---|---|
| 1645年 | イングランド内戦: ネイズビーの戦い。 |
| 1926年 | ブラジルが国際連盟を脱退。 |
| 1940年 | 隅田川にかかる可動橋・勝鬨橋が完成。 |
| 1949年 | 映画倫理規定管理委員会(現 映画倫理委員会)が発足。 |
| 1966年 | 結社の自由及び団結権の保護に関する条約(ILO87号条約)が日本に対して発効。条約自体の発効日は1950年7月4日。 |
※ランダムで5件表示されます。今日誰が何をした日?一覧へ
| 語られているテーマ一覧 |
|---|
 全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
珍しい名字について語りまし…
|
 全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
名字について情報がほしいで…
|
 全国/
その他
全国/
その他
|